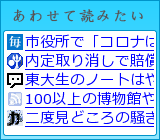柳原慧 / 宝島社
柳原慧 / 宝島社第2回「このミステリーがすごい!」大賞受賞作。1次選考で応募原稿を読んだのは他の人なので、読むのはこれが初めてだ。
誘拐を扱った話だと聞いていたし、「誘拐」というキーワードは全編にわたって使われているのだが、実際に読んでみると「誘拐もの」という印象は薄い。とにかく次から次へと事態が大きく動いていくので、誘拐なんてのはとっかかりに過ぎないように感じる。
これは本書の大きな魅力だ。スタートからは想像もつかない着地点。そこへ至る道筋は決して端正ではないけれど、次から次へと繰り出される新展開に翻弄される楽しさに満ちている。
それだけに、コンピュータ周りの記述については少々残念だ。
不正確ではない。むしろ、今までに書かれたこの手の小説の中でもきわめて正確な部類に属するだろう。登場人物の使うコンピュータは、たいていの場合OSが明示されている(それがLinuxだったら、ディストリビューションまで明示されている)。ある人物はメールを読むのにOutlook Expressを使い、また別の人物はEmacsでMewを使っている、なんてことも書かれている。
だが、ここまでやる必要があったのだろうか?
正確さを重んじたせいか、「描写」というよりは「説明」になっている。そのせいか、ネットワークに接続したりメールを読んだり添付ファイルを開いたり、という場面を読んでいると、なんだか解説書の操作手順を読んでるみたいな気分になる。
それなりに複雑な技術を駆使する場面になると、抽象的な説明にとどまっている。いったい女刑事はどんなコマンドを使ったのか? 他人のPCに侵入したスーパーハカーはどんな内容のプログラムを書いたのか? それらのディテールは希薄だ。詳しく書いても読者が難しく感じるだけだ、といわれるかもしれない。だが、片鱗を示すだけでも説得力が増したのではないだろうか。
たとえば『クリプトノミコン』のような作品では、主人公の技量を示すために、彼が高度なテクニックを駆使する場面を丁寧に描いている(画面の表示内容を「盗聴」されているコンピュータの上で、その「盗聴」を出し抜くプログラムを作るくだりなど)。対象の難しさと、それをクリアする手段。その両方を丁寧に描く演出のおかげで、彼の凄腕ぶりが、コンピュータ技術に明るくない読者にも伝わるのだ。
と、否定的なことをいろいろ書いてしまったけれど、秀作であることは間違いない。いかがわしくも善良な連中の一攫千金の賭けと、誘拐が誘拐でなくなる特異なシチュエーション。そこから紡ぎだされるスピーディな展開は、読者を楽しませることに徹していて、すんなりと入ってゆけるだろう。