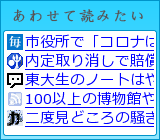【SF】
■矢追純一的宇宙人と時代小説が、ジュニア小説*1の上で出会う
時は江戸時代。日本各地で空に浮かぶ光る物体が目撃され、また物体に人が誘拐される事件や、家畜が切り刻まれる事件が続発していた。幕府は調査のためにひそかに「青奉行」という機関を設けて、光る物体---「虚船」の謎を調査していた。家畜が切り刻まれる現象は「キャトルミューティレーション」、宇宙人に誘拐されて謎の手術を施される現象は「アブダクション」として、矢追純一などの著書でしばしばとりあげられるできごとである。
本書は、そんなキャトルミューティレーションやアブダクションをやらかす宇宙人と、幕府の秘密組織との戦いが描かれる(幕府が宇宙人と密約を結んだりはしていないようだ)。宇宙人に誘拐された人間には、ちゃんと謎の物体が体内に埋め込まれる(何が「ちゃんと」だか)。
アイデアとしては非情に面白い。ただし小説としての描写が弱いと、この手のバカバカしい思いつきによりかかった作品はあっという間に読むに耐えないものになってしまう。本書では、地に足のついた時代小説的な描写と、ジュニア小説的な「軽さ」が同居している。このアンバランスな取り合わせ、一歩間違えば支離滅裂になりかねないと思うが、そこは巧みに乗り切っている。もっともクライマックスには巨大ロボットらしきものまで登場するので、時代小説好きには不満もあるだろう(そんな人がこの文庫を手に取ることはあまりないと思うが)。
著者はイギリスのTVシリーズからアイデアを得たそうだが、クライマックスの描写などを読むかぎり、国産特撮ものの影響も強いような気がする。
*1 : 2008/01補足:当時の私にとって、「ライトノベル」という語句はまだなじみのないものだった。